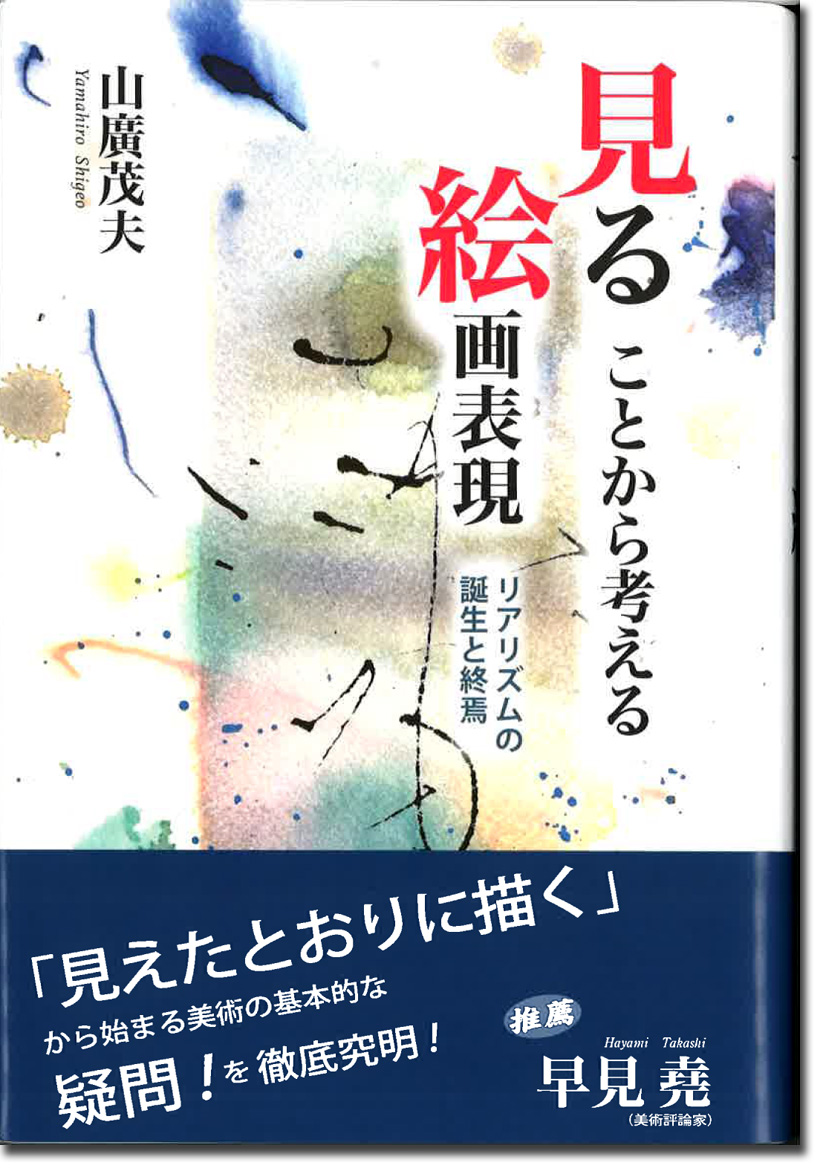
山廣茂夫氏の新刊『見ることから考える絵画表現 リアリズムの誕生と終焉』に関して、美術評論家の早見堯氏が寄せてくださった書評です。ありがとうございます。
「見ることから考える絵画表現 リアリズムの誕生と終焉」早見堯(美術評論家)
私たちが見ている世界と写真や映像の世界は別物と言っていいくらい違う。どうしてだろう。陰影法や遠近法はヨーロッパだけの地域的で特殊な表現方法なのに、なぜ世界標準になったのか。著者は、こうした見ている世界と表現された世界との大きな違い、そして、特殊な陰影法や遠近法が美術世界でどうして標準化されたのかという二つの疑問を中心にして思考を進めていく。
それらはどこでどう誕生し、ヨーロッパ独自の陰影法や遠近法を駆使した「見えた通りに描く」リアリズム絵画へと展開したのか。にもかかわらず、十九世紀末にはリアリズム絵画は破綻してしまい、陰影法や遠近法に依拠しない抽象絵画が二十世紀に生まれた。なぜそうなったのだろうか。疑問は尽きない。
疑問の発端は、浪人中の学習のなかで経験したモチーフを見て見えた通りに描こうとして、じっくり見ていると、ディテールや、明暗の階調(トーン)と色彩、そして周囲の空間までも、見直すたびに違って見えてしまったことだ。これらすべてを描くことはとてもできない。浪人生にもかかわらず、ヨーロッパのリアリズム絵画が行き詰まった頃のルノワールやセザンヌ、ボナールと同じように描けなくなってしまう。なぜなのだろう。自分が見ているもの、あるいは見ていると思っているものはどういう仕組みでそう見えるのか、あるいは思えるのか。不可思議感は増すばかりだ。
疑問はまだある。石膏デッサンで立体感や陰影法がどうしてあれほど必要とされているのか理解できなかった経験だ。すでに破綻しているはずの陰影法や遠近法による表現は、いまだに絵画表現の基礎とされているのも気になる。ヨーロッパだけに発達した陰影法と遠近法が、ここまで広範に美術世界を席巻した理由はなんなのだろうか。
著者は次々とわきおこってくる美術学習での切実な疑問への答えを求めて、知覚心理学の助けを借りながらヨーロッパ美術の淵源へと遡る旅を始める。解答は得られるのだろうか。疑問への解答を求める思考のプロセスを著者と共にたどっていると、まるで上質な推理小説を読むときのようなスリリングな高揚感とときめきを感じる。読み初めると興味をそそられて尽きることがない。ふとわれにかえると、著者の思考のリズムにいつの間にか引きずりこまれて共に考えている自分の姿に気づくのである。
まず、ヨーロッパ美術を冷静に眺めた「美術の物語」のゴンブリッチや、知覚心理学のギブソンの見えた通りの像を修正する「恒常視」と共に「見えた通りに描く」ことの不可能性を解明する旅にでる。見てそして理解した知覚像と見ているはずの網膜像との差、あるいは溝を解明していくのだ。知覚像と網膜像は、たとえば、ハル・フォスターの社会的事実として形成されるヴィジュアリティ(視覚性)と、身体のメカニズムによって形成されるヴィジュアル(視覚)に該当するだろう。しかし、この二つをはっきり区別することはできない。相互に分かち難く結びついているからだ。
では、見えた通りに描くことはなぜ不可能なのか。見るは「見なす」という意味で使われるように、「考える」や「思う」を意味している。だが、ヴィトゲンシュタインの独我論風に言えば、同じ場で同じものを見ていても隣の人が何を見て何を考えているかはわからない。そこにフロイトを加えれば、自分が見ている(考えている)ものは何なのかは、私が関わることができない無意識がコントロールしているので自分すらわからない。何をどう見ているのかは自分も含めて誰にもわからないのだから、見た通りに描くことなどできるはずがないということになってしまう。それが、フロイトと同時代のヨーロッパの十九世紀末の先端的な絵画の状況だった。
だから逆に、「見えた通り」の像を誰にでもわかるように標準化する方法のひとつとして陰影法や遠近法が生まれたと考えることができる。特にルネサンス期に活版印刷で使われた銅版画の線による陰影表現、そして新発明の遠近法が、解剖学や光学機器の助けを借りながら、「見た像」を「考えた像」として様式化して絵画の陰影法を生み出したということになる。ここで、本来は一体化していたはずの見ることと考えることが分断されるようになったのだ。マクルーハンが「グーテンベルクの銀河系」で活版印刷の功罪のひとつは感性と知性を分断したことだと書いていたのが思いだされる。活版印刷は、本来、一体化していた見ることと考えることの間に溝を作りだしたというのである。
著者は「見えた通りには描けない」、あるいは、「見ることと考えることの溝」の転回点をセザンヌに同定している。セザンヌは、そのときそのときに見た像を画面に構成しなおすことによって、見ることと考えることをあらためて一体化させた。すなわち、セザンヌの言葉では「感覚を実現」しようとしたのだ。
見えた通りに描くことを断念して「見る」と「考える」を一体化させるとはなんという逆説だろうか。そうすると、問題は、「作者」は何を描いているのかということから、「絵画」をどう描くのかということへと展開していく。中心は「作者」の独創性から「絵画」の独自性に転換する。では、その「絵画」の独自性とはそもそもなんなのか、あるいは、そうした絵画を成立させているものは何かという疑問へと続いていったのだ。
そのとき、現代美術の源泉の一人となっているデュシャンが登場する。「見えた通りに描く」はデュシャンにおいては、網膜絵画として拒絶されたと著者は指摘する。網膜絵画は作者の網膜に映っているイメージにもとづいている。したがって、網膜絵画の拒絶とは、作品が作者によって作られるということの否定なのである。では、誰によって作られるのか。神が作るのでもなく、美術作品が美術作品を作るといった二律背反に陥る道を選ばないのだとすると、観客が作るのである。観客が作品をどう見るのかによって作品は決定されるのである。絵画を成立させる根拠、つまり、絵画のアイデンディティを問題にする現代美術の出発点のひとつがここで登場したのだ。
こういう風に、本書では、疑問と解答、問題発掘・問題提起と問題の解決策が次々に展開される。解決不可能な難しい事柄が易しく紐解かれる。著書の筆は私の思考をとらえ誘導していく。そこに推理小説のような興味をそそってやまない面白さがある。
私は、ここでは、本書で扱われている「見えた通りに描く」ことの不可能性に焦点を絞ってみた。著者は、「見えた通りに描く」から始まる美術の基本的な疑問を、高校の美術教員であり画家であるという立場、いわば美術教育と美術表現の臨床の現場での経験と実感とをフィードバックさせながらは究明してきた。それを継続、展開して洗練させたのが本書である。本書の特徴はそこにある。
繰り返すようだが、実制作と思考のフィードバック、それによって得られた知見を高校の美術教育の現場で、若者はどう見てどう描きどう考えるのかを肌で感じながら、自分の疑問とそれへの解答を修正しながら展開をしていったのだろう。本書を読み終わって、それらの疑問については、おそらく、永遠に正しい答えを得ることはできないかもしれないと思ったのだが、本書の思考を手がかりにして、今度は、私ひとりで美術思考の推理の旅をしてみたくなった。 もしかしたら、著者が本書を通してもっとも主張している隠された主題は、実は、自分の手(作品を制作する)と目(作品を見る)で考えること、そして、その時々で行く道をふさぐ疑問に、先入観や偏見、標準化された常識などを捨てて立ち向かえば、おのずから答えが得られ、道が開かれてくるということなのではないだろうか。そういう態度が絵画や美術、そして、芸術を成り立たせている根拠なのだと示唆しているようだ。
『見ることから考える絵画表現 リアリズムの誕生と終焉』
山廣茂夫 著
仕様:四六版/344頁 口絵カラー16頁
定価:2900円+税
2024年1月6日発行
ISBN978-4-910793-06-1 C0071 2900E


Pingback: 年末と新刊発行2冊 | 風人社の窓