続 鍋のなかの解剖学
藤田恒夫著
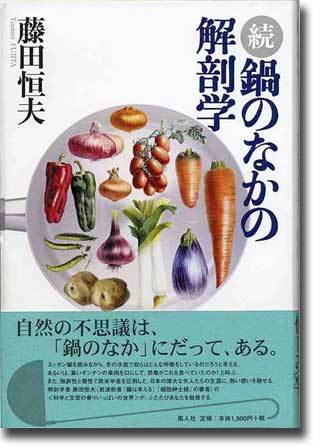
発行:風人社
仕様:四六判 上製本 240頁
定価:本体1,900円+税
2006年7月7日発行
ISBN9784-938643-25-1 C0040 P1900E
装幀:高麗隆彦
スッポン鍋を囲みながら、冬の水底で奴らはどんな呼吸をしているのだろうと考える。あるいは、臭いギンナンの果肉を口にして、恐竜がこれを食べていたのか! と叫ぶ。また、独創性と根性で欧米学者を圧倒した、日本の偉大な先人たちの生涯に、熱い想いを馳せる。 解剖学者 藤田恒夫(岩波新書『腸は考える』『細胞紳士録』の著者)の 科学と文芸の香りいっぱいの世界 が、ふたたびあなたを魅惑する。
著者紹介
藤田恒夫(ふじた・つねお)
解剖学者・内分泌学者。新潟大学名誉教授。1929年生まれ。東京大学医学部卒業。同大学院修了。医学博士。国際形態科学会会長、アメリカ解剖学会、イタリア解剖学会名誉会員、生命科学の総合誌「ミクロスコピア」の編集・発行人。日本ペンクラブ会員、エッセイストクラブ会員、日本味の会会長。学生時代から絵画(油絵、裸婦デッサン)に打ちこみ、個展数回。著書に専門書の他、『Let’s ダ・ヴィンチ』という美術書もある。
※2012年2月にご逝去されました。藤田先生のご冥福をお祈り申し上げます。
本書の目次
第1章 鍋のなかの不思議
スッポン鍋を囲んだ夜
渋い話
新津市から車で三十分ほど南下したところに、蛭野というところがある。昔は石油で栄えた新津の町に近い、山ぎわの扇状地で、ヒルがたくさんいたことからこの地名がついたという。ここにイチョウの大樹が百本あまり群生しており、新緑も黄葉も、それは見事だ。秋には、村人が樹下に銀杏を売る風景もみられる。
三年前の秋、十月十日、わが歯科大学で屈指の博物学者、熊倉雅彦君をさそって蛭野を訪れた。このたびは、一つの研究が胸にあった。
イチョウの実(銀杏)の果肉の部分、くさいですね。あの部分を食べてみようという研究なのである。あのふくよかな果肉は、動物に食べられて種子を遠くへ撒きちらしてもらうためにあるとしか、考えられない。あのにおいも、動物を誘うためのものだろう。とすれば、果肉の味は? というのが当然の疑問である。自分で食べてみるのが一番良い方法だろう。蛭野のイチョウの木の多くは、地面にとどくほど低く樹を伸ばしている。手でとるには好都合だ。黄金の鈴のような実の、ふくよかで色づきのいいのを選んで手にとる。ムッと来る臭気をかき分けるように顔を近づけ、果肉の小片をかじってみた。かなりの甘さと優しい酸味が口の中にひろがった。
しかしそれは一瞬のことで、たちまち強烈な渋味が襲って来たのである。吐き出しても、口腔粘膜がワニ皮になったかと思うほど、こわばったのだ。
この実験、好奇心あふれる博物学者であり、私の護衛者をもって自任してくれている熊倉君のこと、決して私の行動を傍観してはいない。私の行動をみながら、私とほとんど同時に口に入れたのある。彼は私がダウンしているのを横目に、もう一つ、またもう一つと、ちがう熟れ具合の実を食べて、結局私の十倍の量は口に入れただろう。どのくらい呑みこんだかは知らないが。
私はと言えば、わずかな量を口に入れ、そのごく一部を呑みこんだだけなのに、胸の真中に太い棒をさされたような違和感が、その日一日中去らなかった。食道の内面がタンニンで固定されてしまったという感じだった。
だから、熊倉君が翌日、フツウの顔で大学に現れた時は、心底ホッとした。しかし彼が「先生お互い生きていましたね」と言ったところをみると、彼も相当のタンニンのダメージを受けたのだろう。要するにこの実験の結果は、私の仮説を半ば支持し、半ば疑わせるものとなった。イチョウの果肉はフルーツのような味(甘みと酸味)をもち、多量の糖分は動物の栄養として貴重なものになりえるが、強烈な渋味があって、たいていの動物は辟易するだろう、ということだ。
たしかに、イチョウの実が一面に落ちていても、それを食べに来ている動物の姿は見ない。カラスだって寄りつかない。アリさえもたかっていないようだ。もっともイチョウの研究家、堀輝三先生によれば、タヌキの「かくし糞ぐそ」のなかに銀杏(種子)を見ることがあるということだが、これも数個を数えるだけのようだ。
そこで最後の可能性として、現代の動物が食わないとしても、太古のジュラ期に、イチョウと共に繁栄していた恐竜がこの果肉を好んでいた、ということも考えられる。
動物の中に渋味に抵抗できる仕組みや体質をもつ種があれば、イチョウの実や渋柿をモリモリ食べて生存競争に勝てるだろうが。それにしてもイチョウも、これだけ大量の果肉と糖を目的もなく捨てているとは、一体どういうことだろう……と、疑問の迷路はまた振り出しに戻るのだった。
--と、恰好よく書いて来たが、実はこの実験、残念ながら先達の実験の追試だったことが判明するのである。
東京大学助手(当時)の植物学者、塚谷裕一氏(現 東京大学教授)。私は存じ上げない方だが、この方のエッセイを岩永敏彦君が、こんな人が先生と同じことをやっていますよと、送ってくれた(日本経済新聞、一九九七年五月五日掲載記事を、日本エッセイストクラブ編、九七年版ベストエッセイ集、文藝春秋、に採録したもの)。さっそく読んでみると、たしかに--。この塚谷先生、イチョウの果肉は動物に食わせるためにあるとの仮説をたて、食べてみようと思い立ったというのである。
ここまでは私と全く同じで、いや、知らなかったとはいえ、私が塚谷先生の真似をしていたことになるので、恥ずかしく残念な限りだが、そのあとの展開はちょっとちがったのである。
塚谷先生は、自分が食べてみようという気は全くなく、学位論文のことで先生に弱みを握られている学生を、おどしたりおだてたりして試食させたと書いてある。弱い立場の学生がついに観念して、くさい実を口に入れる横で、「どう?」「どんな味?」ときいている(これもリアルに書いてある!)先生とくらべると、熊倉君という「共同研究者」を伴っていたとはいえ、敢然と自分のからだで実験した私は、ちょっと威張ってもいいかと思うのだ。
塚谷先生のエッセイでは、先生がイチョウも柿と同様、渋イチョウと甘イチョウがあるのではないかという「第二仮説」を立てて、研究を続けているが、そのなりゆきを報告する紙面は切れた、と終わっている。しかしこの第二仮説は甘い、と私は思う。紙面が切れたというのは、ほっこりした結果がでないということだろう。(甘イチョウなど、あるものか!)
一方、私たちの第二計画は、全く独自のアイディアである。「おけさ柿」(佐渡特産のさわし柿、甘くておいしい)のようにイチョウの実の渋抜きができないだろうか、という研究なのだ。
熊倉君と私は、秋が深まるたびに蛭野からくさい実をとってきて、アルコールを吹きかけたり、焼酎に漬けたり、いろいろの処理をして、さて試食してみるのだが、結果は甘くはない。今のところ、成功の兆しさえ見えていない。
しかし、もしイチョウの実の渋抜きに成功したら、全く新しい食品、おそらく「日本のドリアン」の誕生である。工業化できれば、利益は莫大なものとなるだろう。
どなたか、渋抜きのいい知恵、ありませんか。もうけは山分けで。
(本書より)
不潔感の民族学
私の手は猫手
牧子さんの咳払い
イチョウの精子
第2章 独創性への畏敬
小さなレンズを磨いた男
細胞を発見した物理学者
アドレナリン発見から百年(1)
アドレナリン発見から百年(2)
田原淳先生の独創性を思う
オッディのペルジアと田原の安岐町
第3章 研究者として
「脳の時代」の落とし穴
胃の研究の今昔
インスリン発見のあとを辿る
連続の思想(自然は跳躍せず)
下痢と嘔吐を命令する細胞
第4章 旅と絵にみつけたこと
テンプラのふるさと
よみがえれ山古志村
ユニークなアルプス越え
ひとつの「アメリカ物語」
パントゥール・フジタ(絵かきのフジタ)
ホテルのベッド
ドイツのお菓子
引越し物語
樋口加六先生の思い出
裸婦モデルの今昔
第5章 出会いと別れ
早世した情熱の解剖学者
山内逸朗先生を偲ぶ
同病異界の人 團伊玖磨
ミクロ映画の巨匠 小林米作
第6章 日本語で科学を語る
天竺から来た? モルモット
細胞紳士録
日本語が日本人の科学をつくる
ある国際誌の生い立ち
発作から生まれた「ミクロスコピア」
あとがき
取り上げていただいた書評をご紹介しています。






